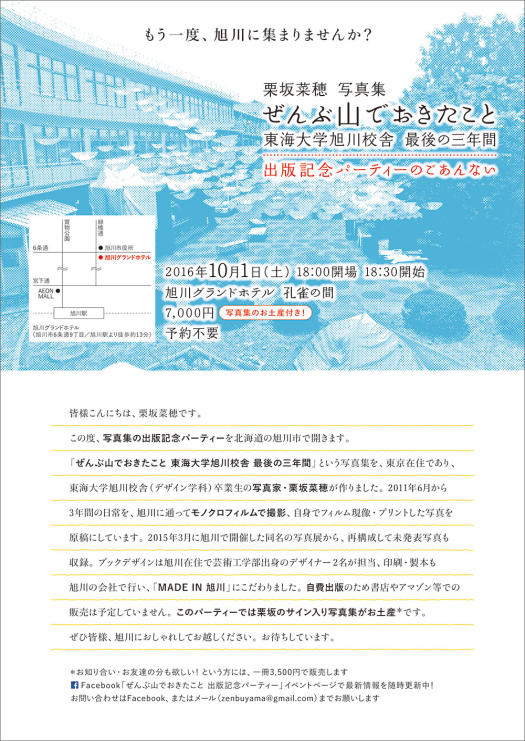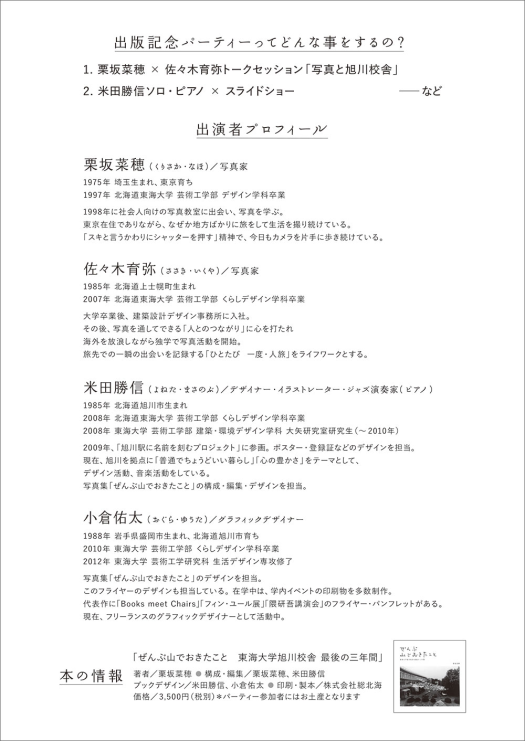10月9日(水)に開かれた、
FONTPLUS DAY セミナー vol.21
「中村書体と筑紫書体」の1日目へ参加してきました。
写研の「ゴナ」や「ナール」の作者である中村征宏さんと、
フォントワークスの筑紫書体で時代を作る
藤田重信さんのお二方によるセミナーです。
私は「ゴナ」「ナール」の大ファンで、
ゴナがDTPで使えるようになる夢を見てしまうほど。
(そのことを懇親会で中村さんにお伝えできてよかった!)
朝起きると使えないことにガックリしたりね(^_^;
筑紫書体に対する熱もここ1年くらいで高まりつつあり、
これは参加するしかないと決めたのでした。
以前よりネット上にて、中村さんの娘様であります
平山知子さんと親しくさせていただいており、
10年ほどの時を経てようやくお会いすることができました。
平山さんからご依頼をいただき、
会場で配布された「ナールのコースター」と、
「中村書体室」の紹介カードの版下データ作成も
お手伝いさせていただきました。
Facebookを見てたら「コースターを額装する!」と
書いておられる方もいてなんだか嬉しかったです。
そりゃ、飾りますよねえ。
写真撮影タイムのときの中村さん。お若い!
セミナー会場や懇親会場でお話させていただきましたが、
とっても優しく謙虚な方で感激しました。
あとあと、セミナーでは触れられていなかったけれど、
会場のスライドで使われたイラストは
全てご自身がIllustratorで描かれたものだとか。
素材とかじゃないんですよ〜。(ここでお見せできないのが残念)
藤田さんとは簡単なご挨拶しかできず……。
懇親会でもっとお話してみたいと思っていたので、
ちょっと後悔が残ります。
セミナーでお二方がどんなお話をされたかは、
他の方のレポートに譲ります。
このセミナーのために東京へ行ってきたわけですが、
書体ファンの友人とカレーを食べたり、
エディトリアルデザイナーの友人とピザを食べたり、
インテリアデザイナーの友人とカレーを食べたり、
神保町の「スマトラカレー共栄堂」でカレーを食べたりして
楽しかったです。東京は人に会うためによく行きます。
本当は来年また行きたいくらいなので、
そのときもみなさん仲良くしてくださいね。
あと、いま台風が心配なので、
みなさんご無事でいられますよう……。
ではでは。